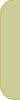

| 2001年9月にホームページ『駒の詩』を開設してから、早いもので8年目を迎えています。ありがたいことにこのHPへのアクセス数も、2009年3月現在で13万もすでに超えています。それだけ多くの駒好きをはじめ、みなさんに認知され支えられてきたことを振り返ると、内心忸怩たる思いがします。 私(酔棋)が駒を作りはじめたのは、第1作が1977年5月に完成ですから、今年(2009年)で30年以上にもなります。私自身もこんなにも駒を作ることになるとは、夢にも思いませんでしたが、今回の個展の出品作を含めて、2009年3月現在で制作数も314作となりました。 制作数300組を超えたのを記念して、今回の「酔棋制作駒『第3回個展』―駒の後ろに作者が見える―」を開催することにしました。これを機に、この『駒の詩』も2009年2月に全面的にリニューアルいたしました。 |
個展開催について
今回の個展のテーマとした「駒の後ろに作者が見える」は、私の「プロフィール」の下段でも紹介しています。この言葉は、漫画家・永島慎二さん(2005年没、「永島慎二レクイエム」参照)が私に言っていた「本当にいい駒とは、技術的なうまさではなく、駒の後ろにその作者の影が見えてくる」をもとにしています。生前、私の駒友でもあり、また「心の師」でもあった永島さんの言葉の意味するところには、私にとってまだ道ははるかに遠いと思います。しかし、少しでも近づけたら思い、今回の個展のテーマとしたわけです。今回出品する駒たちの後ろに、酔棋の影が少しでもちらつけば作者としてはこの上ない喜びです。
駒の制作数が100組に到達したとき、「酔棋制作駒個展―棋は鼎談なり―」(1991年)を開催。また、制作数250組超えを記念して、「酔棋制作駒『第2回個展』―使われてこそ名駒―」(2005年)を開催しました。それらの模様は、「第2回個展メモリアル」をご覧ください。次いで今回の「第3回個展」を、私の地元である東京・高田馬場で開催することにしました。
その詳細は下記をご覧いただくことにして、個展開催に合わせて、「『駒の詩』第4回オフ会」も開催します。そのオフ会の申し込みなどの詳細は最下段をご覧ください。
※少しご面倒をおかけしますが、「第3回個展」の申し込みと、「第4回オフ会」の参加申し込みは、両方おいでになる方も、それぞれ別々にお願いいたします。
|
■開催日時 ■開催会場/東京・高田馬場「割烹・桂(かつら)」 ■お申し込み |
今回は、このHPのトップページに掲載している「巻菱湖虎杢(第300作)」をはじめとする新作の十数作が、主としての展示即売の駒となります。出品作の詳細については、同じくトップページからも入れる「第3回個展出品作」をご覧ください。
なお、これらの新作は、従来どおり「酔棋制作駒作品ライブラリー」にも掲載してあります。十数作の即売の駒の他に、参考出品作や「第2回将棋大会」に使用する駒や賞品なども、会場にてご覧いただけます。参考出品作とは、私の代表作「水無瀬紫雲虎斑(第150作)」と、今回みなさんにご覧いただくために、以前にお譲りした方からお借りした駒です。作品展示は、全部で20〜30作くらいになる予定です。
また、現在駒紹介中の「第12回駒オークション・淇洲虎斑盛り上げ駒」も、会場に展示いたします。さらに、高級駒木地(数点)も用意しますので、ご希望の方にはそれらの駒木地での注文も当日お受けいたします。
|
酔棋駒で将棋を指そう(無料)! ■個展期間中・4月11日(「将棋大会」予選終了後、空いているスペースで) 会場にいらっしゃる方なら、どなたでも酔棋制作の駒で将棋を指していただいてもかまいません。お友達同士でも、会場で知り合った方とでも、忙しくなければ個展役員との対局もかまいません。 4月12日(日曜日)は一日中、酔棋制作駒(「龍山安清虎杢(第195作)・酔棋愛用駒」など)で実際に将棋を指せるコーナー(同時に10人くらい対局可)を設けます。さらに、上記の個展役員と対局(役員は四段以上ありますので、棋力によって駒落ち戦も可)して見事勝った方には、勝利賞(「第3回個展出品駒カレンダー」か、サインした拙著『将棋駒の世界』)を差し上げます。チャレンジしてみてください!
別項の「第2回将棋大会」で紹介している対局用の駒は、どれを使っていただいてもかまいません。 |
 |
水無瀬書島黄楊柾目書き駒 もっと大きな写真を見たい場合は、「フォトライブラリー」の「▼オークション出品・プレゼント抽選・将棋大会」の項目から、作品番号(№309)を選んでください。 |
上記の「水無瀬」は、比較的多く作る書体の一つです。みなさんによく知られている「水無瀬紫雲虎斑」と、この書き駒は基本的にはまったく同じ書体で作りました。ですから、駒木地と製法の違いだけといってもよいかもしれません。抽選に当たってこの駒を手に入れた方は、酔棋流の書き駒をぜひ使ってみてください。
個展会場に展示するこの「水無瀬」は、「酔棋制作駒プレゼント抽選」の「第6回」に該当します。ですから、当選した方の写真や「喜びのコメント」などは、後日「第6回駒紹介」として掲載させていただくことをお願いいたします。掲載する場合のページは、第1回〜第6回までの「プレゼント抽選
」を参考にしてください。
個展会場に訪れたみなさんに、いくつかプレゼントがあります。当日、会場にて販売する「第3回個展パンフレット」(予定価格300円)か「第3回個展・出品駒カレンダー」(2010年度版・予定価格1000円) のどちらかをご購入のみなさん(1人1回)に申し込んでいただき、抽選で1名の方に上写真の「水無瀬書柾目書き駒」をプレゼントします。駒以外では、これから新たに作る根付(書き駒/紫檀・紅紫檀・島黄楊・薩摩黄楊/根付の紐は絹製) 、DVD『駒を作る』、拙著『将棋駒の世界』 、先の「出品駒カレンダー」など全部で10名ほどの方にプレゼントします。
新たに作る根付は表と裏に、「好きな書体」や「好きな言葉」、また自らの「お名前」を入れるなど、当選者のお好みで自由に決めてください。さらに使う漆の色なども、他のページでたまに紹介している根付などを参考に、こちらもご自分で決めてください。
抽選は、個展の2日目(4月12日)の午後5時ころを予定しています。ですから、会場にて抽選に応募する方は、それまでにお願いいたします。なお、今回の「出品駒カレンダー」(2010年度版)は、「第3回個展」を記念して私が気に入っている駒(展示品)のみで構成(12駒)し、新たに正規の印刷で作ってもらうものです(当日までに完成の予定)。
※会場にて、拙著『将棋駒の世界』を持参して、ため書きを望むみなさんは、遠慮せずに私(酔棋)にお申しつけください。合間を見てサインをさせていただきます。
個展会場に訪れたすべてのみなさんに、受付時に抽選(1人1回)していただきます(上記の抽選とは別に)。
 |
 |
| 書体も、実にいろいろな根付。 | 何の書体の歩か考えてみては? |
『将棋駒の世界』の54-55ページ紹介しているように、私がこれまでに作ってきた駒の余り歩が多く残っていました。それを今回、簡易の根付(紐は普及品)にしてみなさんにプレゼントします。通常は余り歩2枚を含めて全部で20枚作りますが、私の場合材料があればだいたい21枚作りますから、さらに余り歩となっていたわけです。
これらの余り歩は、もとの駒木地や製法も実にいろいろです。たとえば素材は、虎斑、柾目、根杢、また黄楊以外の紫檀や黒檀などです。また、製法も盛り上げ駒が多いいですが、彫り駒や書き駒も混じっています。当たった方はその場で、ご自分でお好みの根付を選んでいただきます。私に駒を依頼なさったことのある方は、ご自分所蔵の歩もあると思います。
全部で30個以上用意していますので、当たる確率はまあまあではないでしょうか。携帯のストラップなどにお使いください。
駒の鑑定―古い駒などご持参ください! ■駒鑑定・北田義之(号・如水、将棋駒研究会会長)、増山雅人(号・酔棋) みなさんの中で、もしも比較的古い駒や作者不明の駒をお持ちの方は、個展ご来場の節にご持参ください。北田義之会長と私で、駒の鑑定をさせていただきます。 ※原則として、現在活躍中の駒師の作は、なるべく避けてください。 |
これまでに、「『駒の詩』初のオフ会」(2003年11月、詳細は別項「『駒の詩』第1回オフ会実況!」)、「『駒の詩』第2回オフ会」(2005年3月、詳細は別項「『駒の詩』第2回オフ会実況中継!」)、「『駒の詩』第3回オフ会」(2006年10月、詳細は別項「『駒の詩』第3回オフ会実況!」)を行ってきました。2年半ぶりに4回目の「オフ会」を催すことにいたしました。 ■開催日時 ■第4回オフ会会場 ■参加費用 ■参加申し込み締め切り ■個展・将棋大会・オフ会に関する問い合わせ 原則的には上記のとおり4月11日(土曜)を予定しています。ただし、もしもそのときに都合悪い方がいらっしゃれば、12日(日曜)は少人数でお疲れ会(個展役員が参加)を考えていますので、その旨、参加申し込みのときに、お知らせください。その場合は、参加費用は実費となります。 いい機会ですので、みなさんの参加をお待ちしております。 |