

|
宗歩好島黄楊赤柾盛り上げ駒 この駒は、「名人駒」として世に知られた名駒の中の名駒である。戦後間もなくから、実際に名人戦で使用されてきたから、文字どおりの「名人駒」といわれるようになったのだろう。 ※協力/日本将棋連盟(『NHK将棋講座』の取材) |


「名人駒」(宗歩好)の実際の駒銘は、上の写真をご覧になっておわかりのように、漆が磨り減って判読が不能である。そこで、右に「奥野作」「宗歩好」の駒銘字母を、参考のため掲載しておいた。実際にはハンコが押され、漆で書かれているものが、奥野作の駒銘のひとつの特徴でもある。
ハンコの文字が基礎とはいえ、その漆の流麗な筆致は、豊島龍山の駒銘に匹敵する優美さだ。とくに、漆が歳月によってか、漆そのものか、茶色味帯びやや透けて見えるのは実に味わい深いものである。
| 菱湖書薩摩黄楊柾目彫り駒 (杉亨治氏所蔵)
|
奥野作の駒は、何といっても実戦向きということに尽きると思う。というのは、流麗な駒銘に比べると、一枚一枚つぶさに見る駒字は、大胆すぎる太字であまり優美さは感じにくい。それが、いったん対局で並べられると、目線と盤上の距離がちょうどいいのか、実に指しやすく駒字そのものも見やすく感じさせるのである。面取りがしっかりしてあるのも、実戦を考えてのことかもしれない
対局に使用する道具という宿命を踏まえて、さらにその状況そのものを、あらかじめ計算しているかのような趣を備えているのが、奥野作の駒なのだ。ただの美しいだけの駒は、奥野作の駒に遭遇すると、吹き飛ばされる気がしてくるのは、私一人だけではないだろう。
また、駒形や書体について(下記参照)も、独自の個性を持ち合わせている。これはもちろん推測にしかすぎないが、同時代の駒師・豊島龍山を意識して、その対極に奥野の駒作りがあったのではないだろうか。
 |
|
初代・奥野一香 (奥野藤五郎) 1866〜1921年 |
東京・芝宇田川町で「奥野一香商店」という盤駒店を営んでいたのが、初代・奥野一香こと本名・奥野藤五郎(1866〜1921年)である。商店のブランド名であり、駒師としての号が奥野一香なのだ。藤五郎は将棋四段で、2代目の息子・幸次郎(1899〜1939年)は、名人駒師と称されるほどの名工だったという。現在、その奥野家には、盤は残されているものの駒に関する資料や道具は、残念ながら見あたらないという。
別項で紹介している豊島龍山と奥野は、ほぼ同時代を過ごした。その龍山と技を競うためか、後述する独特の駒形をはじめ、奥野は独自の駒作りをめざしていたようである。
先の「宗歩好」は、江戸時代から伝わる「安清」という書体を奥野流にアレンジし、「宗歩好」と命名したと思われる。また、龍山が売り出した通常の「錦旗」(「書体への誘い・錦旗」参照)に対抗して、かつてからあった「昇龍」〈三味線弾きが本職で、将棋好きで能書だった昇龍斎の駒銘)という書体を改良し、同名の「錦旗」という駒銘で販売したという。それが、下記の抜粋字母(玉将、歩兵、と金、錦旗駒銘)である。
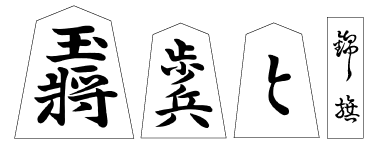 |
|
奥野作の「錦旗」の抜粋字母と、「錦旗」の駒銘。
|
歴史的名勝負として知られた名人戦(昭和46年第30期)の大山対升田戦で、「升田式石田流」が出現したときに指されたのが、この奥野作の「錦旗」である。東京の「福田家」(現在では対局は行われていない)所蔵の「錦旗」が、その歴史の一翼を担ったのだ。その駒は鮮やかな虎杢だから、「新手一生」を標榜した升田がその駒を手に盤上で舞う姿を想像するだけでも、将棋ファンのみならず駒マニアにとってもたまらない光景だろう。
また、この「錦旗」は、現在では通称「奥野錦旗」(私の作だが、「作品ライブラリー・奥野錦旗/第287作」参照)として、ことにアマチュア駒師にはなかなか人気を博している書体の一つだ。勇壮でもちろん盛り上げにぴったりの書体だが、彫り駒にしても味わいと個性があり、意外といいものである。
ここで紹介したこれらの書体に限らず、奥野作の書体はすべて奥野流にアレンジされているといっても過言ではないだろう。その個性は駒形にも表現されている。奥野の書体で実際に作ってみればわかることだが、通常の駒形で作るとどことなく違和感を覚える。というのは、下の末広がりの角度が、宮松影水などに比べると、極端に鈍角なのである。実際には微妙な差なのだが、こんなところにまで奥野流が貫かれているのだ。