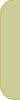

羽前島黄楊柾目書き駒 |
 |
 |
「玉将と歩兵」のアップ。 |
今回の「羽前」は、私(酔棋)としては比較的制作数が少ない書体だ。同じ「作品ライブラリー・羽前島黄楊絹柾書き駒(第324作)」(▼別項参照)と「第18回オークション出品駒・羽前島黄楊杢盛り上げ駒(第367作)」(▼別項参照)で、今回で3作目となる。以前にも書いたことだが、「羽前」に関しての詳細を以下に再掲する。
――辞書などによると「羽前」とは、「旧国名の一。明治元年(1868)出羽(でわ)を羽前・羽後と南北に2分した南の部分。東山道13か国の一。現在の山形県の大部分にあたる」と書かれている。だから、現在では将棋の町として知られる山形県天童市なども含まれるのかもしれない。よってその地方の書体とも考えられるが、この書体の原本は「豊島作」(「書体への誘い・豊島龍山」▼別項参照)の盛り上げ駒であったので、現在も天童に伝わる伝統的な書体とは趣を異にしている。
これはあくまでも推察にすぎないが、豊島龍山が当時の山形の駒に影響を受けて字母紙を作ったものではないだろうか。他に「羽前」を作っていた駒師としては、「木村作」(「書体への誘い・木村文俊」▼別項参照)も、私はかつて見たことがある。その書体は、もう少し無骨な感じがした気がする。筆の流れの強弱(太い細い)が、得も言われぬって魅力となっている。「玉将」をよく見ると、下の「将」の字が末広がりなところは、江戸期末期をはじめとする昔日の駒によく見られる特徴ともいえよう――
前2作とは異なって、今回は「島黄楊柾目」の通常の駒木地でも、拭き漆仕上げにしてみたが、その趣は感じられるだろうか。また、「羽前」の特徴である駒字の太いところから細い流れの漆が表現できているだろうか。何作か作っても、そのたびに新しいテーマが生じるのが、駒作りの興味深いところだ。
※もっと大きな写真を見たい場合は、「フォトライブラリー」(▼参照)で、「作品ライブラリー・№475」を探してください。