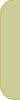


 |
| 左が磨き上げた実物の「金将」の裏。真ん中は磨き上げていない紫檀の駒木地。右は黒檀の駒木地で、縦縞の濃淡が見える。 |
 |
 |
| 隷書の「玉将」と「歩兵」。 | 篆書の「と金」。 |
写真(左)の「玉将・歩兵」を見ればおわかりのように、表字は隷書、裏字は篆書のコラボレーションが「無劍」の持ち味で魅力でもある。人が何かを持ってバンザイしているように見える、ちょっとユーモラスな写真(右)が、特徴ある「と金」だ
別項「書体への誘い・無劍」をご覧いただいた方にはおわかりかもしれないが、今回制作した「無劍」は宮松影水のものをもとにしている。
数年前に、知り合いの収集家が入手した影水作の「無劍」にめぐり合って、今度作る「無劍」はそれにしようと以前から決めていたのだ。
同じ作品ライブラリーの「錦旗(第242作)」のところでも少しふれたが、紫檀のような多孔質の素材は、彫り駒には向かないので書き駒で作ることが多い。写真ではわかりにくいと思うが、そのあたりを「金将の裏」(上写真)の駒木地で見比べていただきたい。
そこで、サビ漆で穴(多孔質)を埋めてから拭き漆を施すなど、かなり手間をかけて書き駒の下地をしている。それから色漆を使って書体を転写し、あとは盛り上げ駒と同じ要領で駒字を盛り上げるのである。
ちなみに、今回使用したのは下地の色に合わせて白の色漆だが、実際には完全な白ではなくアイボリーといった仕上がりだ。それが駒木地の色とマッチして、いい感じ仕上がったと自負している。
この駒は私の作る「無劍」の決定版であるとともに、書き駒の代表作といっていいだろう。