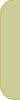


 |
 |
 |
| 素彫りの状態でも、虎杢らしさは十分に伝わってくる。 | 彫り埋めを作るときに、私は生漆+呂色漆+との粉(水)をよく練ったサビ漆を使用。 | 漆を盛り上げるとにき、彫り埋めにほんの少し太めにかぶせる感じで仕上げている。 |
「錦旗」「巻菱湖」「水無瀬」「源兵衛清安」のこれらの4つが、駒の書体としては人気があり、駒収集家がまず集めはじめる書体といえるだろう。ついで必ずといっていいほど1組は持っていたくなるのが、この「長録」ではないだろうか。
この書体は、その由来を書いた「書体への誘い・長録」をご覧いただければおわかりのように、その独特の書の趣(成香がひらがなの「ふ」に見える)から判別がしにくくて、けっして駒字には向いているとは思えないのだが、そのえもいわれぬ魅力は、その欠点を補って余りあるといってもいいくらいである。
駒の書体というものは、駒木地とのバランスもかなり大事だ。この駒のように派手な虎杢で、おとなしめな書体を作ると、駒字が駒木地に負けてしまい、ややアンバランスな感じを受ける。「長録」ように個性が強い書体は、どのような駒木地で作っても、駒字としての存在感を醸し出してくる。
これまでに、孔雀杢、虎杢、赤柾、荒柾といった比較的個性が強めの駒木地で[長録」を作ってきたが、どれもそれなりに独特な味わいは失われてはいなかった。
ここで、上の3つの写真をご覧いただきたい。この「長録」を作った過程で、左から彫り、中が彫り埋め、右が盛り上げの工程である。
同じく玉将をはじめとする大駒だけだが、見比べていただくとその雰囲気はおわかりいただけるはずである。