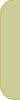

 |
| 上写真左の桐製の箱に、黒柿製の駒箱が収まっている。下写真の黒柿の駒箱は、現代のものに比べるとやや長方形に作られている。厚さも薄めに作られていて、黒柿の味わいが何ともいえず、上品さを醸し出している。 |
 |
 |
▲水無瀬形真龍造(上写真) |
 |
駒銘はすぐ上の写真を見ておわかりのように、漆が入っていなくて彫りっぱなしの状態である。まれにだが、このような彫りっぱなしの駒銘は他にも拝見したことはあるが、かなり珍しいといえるだろう。右はからくも読めるところから「真龍造」と判断できるが、書体名と思われる左が判然としない。「将棋駒研究会」の北田義之会長に、この写真を見てもらったが、やはり確定できなかった。もしも、このページをご覧いただいて、わかる方がいらっしゃったらメールにて私(酔棋)にご連絡いただきたい。
この駒は、左に紹介している二重箱(黒柿製の駒箱が桐箱に収められている)に入っていた。桐箱には墨で書かれた文字があるのだが、これも判読はできなかった。ただ、このような二重箱に入っていたことからすると、それなりの地位の方が使っていた駒なのだろうか?
「真龍」とは、江戸期から明治期にかけて、駒を作っていたとされる人々の一つの号であったとされている。だから、特定の人物というより現代でいうところの駒師工房なのかもしれない。右写真で紹介している2つの駒は、拙著『将棋駒の世界』(▼別項参照)107ページにも掲載してある。
「古い水無瀬」に似たような書体に「真龍造」と入った駒と、「董齊書」と駒銘に入っていて書体が今回取り上げた駒と似通っている駒だ。これはあくまでも推測にしかすぎないが、これらの3つの駒は、何か関連しているような気がしてならないのである。
「書体不詳真龍造」の駒を字母紙に作り直し「真龍董齊書」(第9回駒プレゼント・書き駒/▼別項参照)とでもして、今度新しい盛り上げ駒を作ってみようかと考えている。
※後日、掲示板にて「かかし」さんという方が、「董齊書(ここに掲載した書体不詳・董齊?のこと)は真龍の作で間違いありません。真龍は大橋本家の駒師として、宗桂・宗金の駒を作っておりました」とコメントを寄せていただいている。